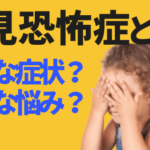脇見恐怖症を治す方法|克服者の共通点とは?[体験談]
- 脇見・視線恐怖症を改善した人に共通した経験
- 人と関わる機会を増やす具体的な方法
- ザッキーの体験談
今回は
「視線恐怖症や脇見恐怖症が改善できた人にはどういった経験や共通点があるか」
をお伝えします。
なぜ、僕がそんな話をできるかというと、
僕は普段カウンセラーとして毎日さまざまな人たちのご相談に乗っていて、
また悩みを抱えている人たちのコミュニティも運営することで多くの人たちと関わっています。
僕自身が元々脇見恐怖症で悩んでいたこともあり、同じ視線に関する悩みを抱えている方のご相談に乗ることも多いです。
そして、たくさんの視線恐怖症や脇見恐怖症と中長期的に寄り添っていく中で、悩みや症状が改善していく方も多く見てきました。
今回はそんな、悩みを改善することのできた人たちの色々な経験の中から、
今現在悩んでいる人たちに対して役に立つ情報をまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。

〜目次〜
脇見・視線恐怖症を改善した人に共通した経験とは?
症状を改善していった人に共通することは何かというと、
【人と関わる機会を増やして対人場面で解決していく】

ということです。
人と関わる機会を増やしていくのは症状改善において大切です。
症状のせいで人との関わりを減らしたり、迷惑をかけてしまうと思って人と関わることをやめたり、自分から対人場面を避ける行動をしてしまっていませんか?
実はそのように回避する行為は、さらに対人に対しての苦手意識を強化してしまって、回避グセもついてしまいます。
回避することで、人に会うことが少なくなり、つかの間の安心感は得られるのですか、症状は維持したまま恐怖心は高まるばかりになってしまいます。
では、なぜ人と関わる機会を増やすことで症状を改善していけるのかというと、
脇見・視線恐怖症の根本の悩みとして、
「人から否定的な評価を受けたくない」
という考えが根本にあるからです。
症状に悩み始めたきっかけは人によって様々だと思いますが、
「過去の経験のなかで、対人が怖くなる大きな出来事があった。
もしくは何度も否定的な評価を受ける出来事が繰り返された」ということが多いです。

例えば
- いじめを受けた経験
- 悪口を言われて仲間はずれにされた経験
- 人前で失敗した経験
- 両親から否定的に育てられてきた
このように何かしらの人から否定的な評価を受けたことがあまりにも強すぎて、「人からどう見られているか」ということを強く意識してしまっている方が多いです。
また習慣的に否定的なことを言われ続けたり、育った環境がそういうところだったこともあるかも知れせん。
そのような経験から色々な対人場面で、過剰に被害妄想的な解釈をするようになってしまいます。
例えば
実際に悪口は言われてないけど、
「悪口を言われているような気がする」と感じたり、

目の前の人とただ視線が合っただけで、
「自分が威圧感を与えてしまっているんじゃないのか」と感じたり
隣の人が咳払いしたり、貧乏ゆすりしただけだけで
「自分がここにいるからイライラしているんだ」
と感じるようになってしまいます。
こういった考えを根本のところから解決してくためには
「人は怖い存在」という認識から
「そんなに怖くない存在」という認識に変えて、
そして「安心・信頼できる存在」へと変えていくことが大事です。

心理療法や、カウンセリング、セルフワーク、心理学の知識をつけることももちろん大事です。
一人で本を読んだり、このような記事などから情報を集めて、知識を学ぶことももちろん大切ですし、それで良くなる方もいますが、ほとんどの方が対人場面のなかで改善していく方が多いです。
人と関わる中で解決していくんです。
「人と関わる機会を増やす」という成功体験をつかむことことで、トラウマ経験を上書きしていって、否定的な評価の恐れが少しずつ和らぎ、症状が改善できるようになります。

どのように人と関わる機会を増やしていくのか?
それではどのようにして人とかかわる機会を増やせばいいのでしょうか。
実際にこれまで脇見恐怖症•視線恐怖症の症状を改善していった人たちの声から大きく分けて4つ説明していきます。
①趣味や自分が熱中できるサークル、交流会に参加

人と繋がれるものであればどんなものでもOKです。
スポーツ系などアウトドアのものでも良いですし、映画やアニメ、漫画など、趣味で繋がれるものでもOKです。
実際僕もサッカー部に所属していたり、大学もボランティアサークルに参加したりしていました。
好きなジャンルのものであれば、熱中ができて、症状に対するとらわれが薄らぐ感覚がありました。
また同じ好きなもので繋がれる仲間なので、他の場で出会う人よりも信頼しやすかったり、共通の好きなものがあるので、雑談もしやすくて友達になりやすかったりしました。
そのなかで脇見恐怖症の悩みがありながらも、いろんな人と関わって、
他人の優しさに触れたり、案外人って怖くないんだという実感がわくことがありました。
これまでカウンセリングをして実際に症状がよくなった人の声として

いろんなコミュニティーに入って人と関わる機会ができた。自分よりも頑張っている人と関われて、自分も頑張ろうと思えた

自己開示をして人との信頼関係を作ったことで、症状自体も緩和できた。人と素のコミュニケーションをとっていくことが大事だと思う
こういった声もあります。
素の自分で自己開示していって、受け入れてくれた体験、友達が増えた経験から症状がよくなった方は多いです。
②悩みを打ち明けられるコミュニティやオフ会に参加

趣味やサークルなどのコミュニティには症状が気になって参加できなさそうだという人は
同じように悩んでいる人たちのコミュニティやオフ会に参加するのもありです。
症状がわかる人同士であれば、あなたの悩みも理解してくれているし、否定的に思われないという安心感があります。
私も悩んでいたときは脇見恐怖症の人たちが集まるようなオフ会をネットで探して参加していました。
初めて初対面の人に症状の話をして、共感してくれた時に感じた嬉しさは今も覚えています。
同じ症状で悩む人同士に対してであれば、症状が気にならないという方もいらっしゃいます。
そこから仲良くなってプライベートでも関われる友人になる方もいます。
実際に症状が良くなった人の声としても

同じ脇見恐怖症の人と複数人で話しているときの感覚を、その後、脇見恐怖症じゃない人と居る時にも少し継続出来ているような気がする
という声もあり、友人や同じ症状を理解してくれている仲間として、安心感を感じたり、そこから人を信頼できる考え方に変わっていくんです。
※同じ悩みを持つ人たちのコミュニティやオフ会の注意点

ただそういった同じ悩みをもった人たちと集まる注意点としては、
「もう症状がよくならないんじゃないか」というような否定的な意見ばかりがでるようになったり、
ただ「しんどいね…」と言いあって共感するだけになってしまうなど、
お互いに依存関係になることです。
そのような関係になってしまうコミュニティやオフ会は避けたほうがよいです。
人は環境の生き物なので、ずっと悩み続ける環境に居続けると、周りに合わせて、無意識で自分も悩んだ状態で居続ける選択をしてしまう人もいらっしゃいます。
また周りに前向きでない人や、「症状は絶対に良くならないし治らない」と思う人がいると、同じように自分も前向きになれなくなってしまいます。
少しずつ症状が改善してきた、症状が良くなってきた、という人はいつまでも悩んでいる人たち同士のコミュニティに居るのではなく、自分のやりたいことに進んでいったり、依存関係から抜け出して、次のステップにうつっていくということも大事です。
③心理学などを学べるコミュニティに参加

心理療法を実践できる環境や心理学の知識を学べるコミュニティ、スクールなどもありです。
「心理学を学びたい」という人には、自分自身がなにかしらの悩みを持っている、あるいは過去に悩みを持っていたという人が多いです。
そのためあなたの悩みに対しても理解があり、受け入れてくれるという方が多いです。
また自分から学びにきているので、悩みを良くしたい、より良い自分になりたいなどの向上心がある方が多く、依存関係ではなく、お互いに高め合う関係になることも期待できます。
また心理学などを学ぶことは、不安を和らげる上でももちろん有効です。
なぜなら不安や恐怖は”知らないこと”から生まれているからです。
症状からくる不安はもちろん目に見えるものではないです。
「なぜ悩んでしまうのかわからない」「原因やメカニズムがよくわからない」「よくなる道筋が見えない」という状態だと、どんな人も不安に感じてしまいます。
まず症状についての理解、対処法などについて正しい知識を得ることが大事で、それを知るだけでも安心につながります。これを専門用語で「心理教育」といいます。
実際僕もオフ会以外に、カウンセリングやコーチングを学べるコミュニティにも所属していました。
そのときは心理学の知識を学べて、悩んでいる原因、メカニズムを知ることができてすごく安心しましたし、自分の悩み改善に活かすことができました。
また、たくさんの人の悩みを聞いて、その人それぞれの辛さや背景を聞いて、他にもこんなにつらい経験をした人がいることを知って、自分自身が直面する出来事に対しても客観的になることができました。
悩みを改善して良くなった人の声を聞けることで、自分ごとに当てはめて参考にして、症状を改善することにも繋がりました。
一人で本を読んで学んでもなかなか実践ができませんし、一人だと孤独感もあってなかなか継続できないので、こういった学べる場所があることは心強いです。
このように自分が悩んできた経験を通して
僕自身現在【WaReKaRaゼミ】というコミュニティを作っています。
様々な悩みを持った方同士が繋がれて、自己開示しあえたり、心理学の知識を学んで症状をグループの力で解決していけるようなコミュニティを作っています。
本の知識だけでは中々解決できないという人、1:1のカウンセリングだけだと改善することが難しく感じる人、同じ悩みをもった仲間と繋がりたいという人にはおすすめの場所になっています。
実際WaReKaRaゼミの方たちからは

悩みを人に話すことが増えた。グループワークやカウンセリングで人と話す機会が多くなって良くなったことを実感している

応援しあえる仲間ができて、他人を”敵”じゃなくて信頼できる”味方”だと思えるようになった
という声があります。
知識を学んで実践していく場があるだけでも、すごく心強いんです。
もしご興味があるかたはこちらのWaReKaRaゼミの詳細をご覧ください。
私がやっているコミュニティ以外に、そういった場所を他に探すというのでももちろんいいと思います。
一人で悩むより、グループで解決していくことで症状改善にすぐ辿りつけます。
もちろん「グループはハードルが高いな」と思う人は、まずは症状を理解しているカウンセラーや専門機関に相談するということでも良いと思います。
④家族や親友など信頼できる人に相談

先程あげたような環境やコミュニティはちょっとハードルが高いと思う方は、まずは家族や親友、学校の先生、同僚、上司など身近の信頼できる人から悩みを相談していくということもありです。
自分ひとりだけで悩みを抱えているよりも、話すことで気持ちがすっきりできます。
もちろん家族や親友は同じ症状に悩んではいないので、もしかしたら理解はしてくれないかもしれません。
ただ話すことで、いままで自分が隠して生きてきた罪悪感から開放されたり、「人に話せた」という勇気になります。
また一人でも受け止めてくれた安心感に繋がって、それが他人に対しての信頼につながるんです。
実際ザッキーも、学生時代はなかなか人に相談できませんでしたが、我慢して初めて友達に話したことによって気持ちが救われた経験もあります。
「大丈夫だよ」とか「そんなのまったく気にならないよ」とか「視線がおかしいとか全く思わないよ」って言ってくれたことで、考え方の囚われに気づけたり、自己肯定に繋がりました。
良くなった方の意見として

「自分の視線のせいで相手に嫌われているかも」と思うのは勝手な決めつけで、相手にとっても失礼だと思ってハッとした。自分が他人を信頼していないんだと思った
という意見もありました。
家族や親友から大丈夫と直接的に言葉をもらえることは、本当に安心できます。
「相手のことを信じよう」「勝手にジャッジしないでおこう」と思えて、それが脇見や視線の囚われから解放していくことに繋がります。
身近で話せそうな人から勇気をもって相談してみてくださいね。
まとめ
今回は脇見恐怖症など視線恐怖症を改善してくためには、【人と関わる機会を増やして対人場面で解決していく】ということをお伝えさせていただきました。
その方法は
- 趣味や自分が熱中できるサークル、交流会に所属してみる
- 悩みを打ち明けられるコミュニティやオフ会に参加してみる
- 心理学などを学べるコミュニティに参加してみる
- 家族や親友など信頼できる人に相談してみる
以上の4つのお話をさせていただきました。
一人で抱え込んでしまってグルグルとネガティブに悩み続けてしまったり、間違った方向に進んでしまうのではなく、人と交流していくなかで解決していくということをおすすめします。
もちろん僕にご相談いただいても大丈夫です。
過去の対人に対しての苦手意識を、新しい対人での成功体験でぬり替えていきましょう。
もちろん症状改善の方法は今回お伝えするものが全てではありませんので、これ以外にもまた改めてまとめていきます。
【自分の視線が気になるあなたへ】脇見恐怖症を克服する3日間動画講座プレゼント
「もしかして、自分の視線で迷惑をかけているかも…」そんな罪悪感や不安に、毎日苦しんでいませんか?
かつて、自分の視線に過剰な罪悪感を抱え脇見恐怖症に苦しんだ僕が、その克服していく過程で学んだ経験から克服方法を3日間の動画講座にまとめました。
この動画講座では、脇見恐怖症の原因となる心理的メカニズムから、視線に対する過剰な意識を手放すための具体的なステップ、日常生活で実践できるトレーニング方法まで、詳しく解説します。
「あの頃の自分を救いたかった」そんな想いを込めて作った動画講座を無料プレゼント!
同じように悩んでいるあなたに、穏やかな日常を取り戻すためのヒントを届けたいです。
将来的に有料化する可能性もありますので、ぜひ今すぐお受け取りください。
↓↓↓