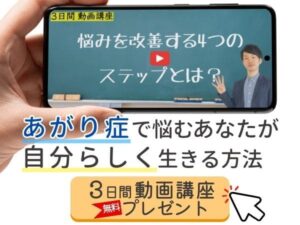【あがり症克服】人前で緊張しない!思考法5選&実践テク12選
動画でご覧になりたい方はこちら。約29分の動画です。
この記事で分かること
- 人前で緊張してしまう原因と、完璧主義を手放す考え方
- 緊張を味方につけるための具体的な習慣と日々のトレーニング
- プレゼンやスピーチで成功するための事前準備と本番での対処法

こんにちは、WaReKaRaゼミ代表「対人不安解消の専門家」ザッキーです
「うわ、どうしよう、頭が真っ白になっちゃった…何話せばいいかわからない!」
「ドキドキしてきた、どうしようどうしよう…手も震えてきた!」
「わー、みんな見てる…視線が集まると緊張しちゃう…」
「えっと、あの、あれです、その…言葉が出てこない…」
こんなふうに、人前で話すことやプレゼンテーションがうまくいかずに悩んでいる人はいませんか?
- 「1対1なら大丈夫なのに、人数が増えると急に緊張する…」
- 「初対面じゃなくても、複数人の前だとダメなんだ…」
実は僕自身も、昔は4人以上の前だと緊張してしまい、頭が真っ白になって言葉が出てこない、なんてことがよくありました。でも、今では10人以上はもちろん、30人、100人の前でも、緊張はするものの、それをうまくコントロールして話せるようになりました。
今日は、そんな僕が実践してきた、プレゼン対策や人前で話すときの考え方、そして具体的な対処法についてお話ししていきたいと思います。「あがり症を克服したい!」「人前で堂々と話せるようになりたい!」そんなあなたのための記事です。ぜひ最後まで読んで、使えそうなものから試してみてくださいね。

〜目次〜
プレゼン・人前で緊張しないための5つの考え方
まずは、人前で話すときの緊張を和らげるための「考え方」を5つ紹介します。考え方を変えるだけで、気持ちがグッと楽になることもありますよ。
1. 完璧主義を手放す

多くの人が陥りがちなのが、「完璧でなければならない」という思い込みです。
- 「絶対に噛んではいけない」
- 「準備したことを完璧に覚えて、スラスラ話さないといけない」
- 「顔が引きつってはいけない」
こんなふうに、「こうあるべき」という自分の理想像や期待が大きすぎると、それがプレッシャーとなって緊張を増幅させてしまいます。そもそも、プレゼンがうまくいかないと悩むこと自体、完璧主義的な傾向があるからかもしれません。「まあ、いっか」と流せる人は、そこまで悩まないですもんね。
では、どうすれば完璧主義を手放せるのでしょうか?
一度、「完璧じゃない状態で話す」という練習をしてみてください。「いやいや、それができないから悩んでるんだよ!」と思うかもしれませんね。僕が試したのは、演劇のワークショップに参加することでした。
そこではアドリブの練習が多く、失敗して当たり前、うまく話せなくてOKという環境なんです。そこで即興で話してみたら、「あれ?意外と言葉が出てくるな」「みんなちゃんと受け止めてくれるんだ」という体験ができました。それが自信に繋がり、「そんなにガチガチに準備しなくても大丈夫かも」と完璧主義を手放せるきっかけになったんです。
大切なのは、失敗しても大丈夫な、安心安全な場所を選ぶこと。初心者向けの話し方教室や、同じ悩みを持つ人が集まる場なども良いでしょう。ハードルが低いところで成功体験を積むことが重要です。
また、他の人の発表を見てみてください。完璧に話している人って、実はそんなにいないと思いませんか?
途中で噛んだり、言葉に詰まったりする人もいるはずです。そんな時それを見て、あなたは「この人、緊張してるな。ダメだな!」とか「止まったな。失敗だな!」と厳しく評価していますか?
おそらく、そんなに気にならないはずです。
もし、「いや他人の噛んだところもすごく気になってしまうんです…」という場合は、その「結果」を見てみましょう。
1回噛んだからといって、契約が破談になったり、評価がガタ落ちしたりすることはほとんどありません。
むしろ、少し噛むくらいの方が人間味があって、親近感が湧くこともあります。噛んだ結果、空気が少し柔らかくなって良い空気になることも多いですよね。
「この人、頑張ってるな。話を聞いてあげたいな」と思われることだってあるんですよ。
2. 緊張して当然!と受け入れる

次に大切なのは、「緊張するのは当たり前」と受け入れることです。
発表が終わった人に「緊張しましたか?」と聞いてみてください。ほとんどの人が「はい、緊張しました」と答えるはずです。
実は、ある程度緊張している方が、良いパフォーマンスを発揮できるというデータもあるんです。「ヤーキーズ・ドットソンの法則」というのですが、完全にリラックスしすぎた状態や、逆に過度に緊張しすぎた状態よりも、程よく緊張している状態の方が集中力が高まり、良い結果に繋がりやすいとされています。
スポーツ選手などもそうですよね。緊張するからこそ、「しっかり準備しよう」という気持ちになりますし、適度な緊張感がパフォーマンスを引き上げてくれるのです。
ですから、「緊張=絶対悪」ではありません。あなただけじゃなく、みんな緊張しているんだということを覚えておいてください。
3. 聞き手は「味方」だと考える

人前で話すとき聞き手のことが、あなたを意地悪な目で評価してくる、まるで敵のように感じてしまうことはありませんか?
でも、考えてみてください。多くの場合、聞き手はあなたの話を聞きに来ている、もしくはわざわざ聞いてくれている「味方」なんです。
例えば、朝礼で話す場合、同僚たちは「今日はどんな話をしてくれるのかな?」と、基本的には好意的に聞いてくれています(もちろん、あなたの日頃の行いや同僚とのコミュニケーションも大切ですが!)。最初から「どうせつまらない話でしょ」と疑ってかかっている人は、そうそういません。
中には、つまらなそうにしていたり、時計を気にしたりする人もいるかもしれません。でもそれは、あなたに対して敵意があるわけではなく、単に「自分のことで頭がいっぱい(例えば、次の仕事の準備など)」なだけかもしれません。良い評価も悪い評価もなく、ただ「そこにいる」だけ、ということも多いのです。
営業のプレゼンなら、相手は商品に興味があるからその場にいるわけですよね?
少なからず「どんな商品なんだろう?」と期待してくれている、まさに味方です。「自分の話を求めてくれているんだ」というマインドで、「よし、この人たちのために話してあげよう!」くらいの気持ちで臨んでみると、少し気が楽になるかもしれません。
よく「聞き手をジャガイモだと思え」なんて言いますが、それも一つの手です。相手を自分より格下に見るというよりは、「赤ちゃんに話しかけるような感覚」で接してみるのも良いかもしれません。赤ちゃん相手に緊張する人はあまりいませんよね?「優しく、分かりやすく伝えよう」という気持ちになれば、自然と話し方も穏やかになるはずです。
4. 「聞き手の視点」を意識してみる

自分が話し手になると、どうしても完璧を求めてしまい、「一言一句間違えてはいけない」と考えがちです。でも、逆の立場、つまりあなたが「聞き手」だったらどうでしょうか?
- 話し手に完璧なスピーチを求めていますか?
- 一言一句聞き逃さないように集中していますか?
おそらく、そんなことはないはずです。「だいたいこういうことを言いたいのかな〜」という感じで、ポイントを掴みながら聞いているのではないでしょうか。
ですので、あなたの話が100%完璧に伝わらなくても大丈夫。
「5割〜7割伝われば御の字」、くらいの軽めの気持ちで話してみましょう。多少緊張していても、「優しそうな人だな」「一生懸命話しているな」と好意的に見てくれる人も多いはずです。聞き手もそこまで厳しくジャッジしていない、ということを思い出してください。
5. 「伝えること」「相手を動かすこと」が目的だと再確認する

そもそも、あなたが人前で話す目的は何でしょうか?
- 朝礼なら → 「最近あった良いことを共有する」
- 営業なら → 「相手に商品を買ってもらう」
これが本来の目的のはずです。「上手に話すこと」や「緊張していないように見せること」が目的になってしまっていませんか?
大切なのは、情報を「伝えること」、そして場合によっては相手に「行動してもらうこと」です。
スティーブ・ジョブズや人気YouTuberのような、プロの話し手になる必要はありません。ただ、言葉を相手に届けるだけでいいんです。営業であれば、商品の良さをいくつか伝えることができればOK。
最終的な目的はそこにあるということを忘れずに、もっと楽な気持ちで臨んでみましょう。
あがり症を克服し、自信をつけるための5つの習慣
次に、日頃から意識して取り組んでほしい「習慣」を5つ紹介します。これらの習慣を続けることで、少しずつ緊張に強い自分を作っていくことができます。
1. 聞き手のタイプを理解し、コミュニケーションを深める

「この人、僕のことをよく思っていないんじゃないか…」と、聞き手を敵だと感じてしまうのは、もしかしたら日頃のコミュニケーション不足が原因かもしれません。
特に、上司や役職のある人の前で緊張してしまう、という人は多いですよね。
これは、相手がどんな人なのかよく分からないために、
- 「自分にも周りにも厳しそうだし、怖い人なんじゃないかな…」
- 「せっかくの機会だから、何かすごいことを言わないといけないんじゃないかな…」
と身構えてしまうからです。
でも、普段からコミュニケーションを取っていれば、
- 「ああ、上司も人間っぽいところあるんだな」
- 「意外とミスもするし、可愛いところもあるんだな」
と分かり、相手を「味方」だと感じられるようになります。
「でも、社長とか役職のある人とは普段なかなか話せない…」という場合もあるでしょう。そんなときは、その役職者と親しい人や、その人のことをよく知る人と話してみるのも一つの手です。
「実はあの社長、こんなお茶目な一面があるんだよ」といった情報を聞くだけでも、少し安心できるかもしれません。可能であれば、飲み会などでプライベートな一面に触れる機会があればベストですね。
また、もし苦手な相手が特定の年代(例えば50代〜60代の上司)なのであれば、その特定の苦手な相手ではない50代〜60代の人と積極的に話してみるのも効果的です。
「年上だから怖い」「役職があるから怖い」という思い込みが外れ、「なんだ、意外と話しやすい人も多いな」と気づけるかもしれません。プレゼンの本番だけでなく、普段から様々な人とコミュニケーションを取る練習を心がけましょう。
2. 自分なりのリラックス方法を意識的に行う

自分に合ったリラックス方法を見つけ、普段から意識的に行うことも大切です。
- 深呼吸: 短くスースーするのではなく、3秒かけてゆっくり息を吸い、その倍の時間をかけて(6秒かけて)長く吐き出す。長く吐くことで副交感神経が優位になり、リラックスできます。
- スージングタッチ: 自分の体に優しく触れること。例えば、胸をトントンと軽く叩きながら「大丈夫、大丈夫」と心の中で唱えるだけでも落ち着きます。
- 筋弛緩法: あえて体にギュッと力を入れてから、フッと緩める方法。肩をすくめてストンと落とす、手を強く握ってパッと開くなど、緊張と緩和を繰り返すことでリラックス効果が得られます。
これらのリラックス法は、本番でだけいきなりやろうとしても上手くいきません。
1日の終わりにやる、出勤前にやるなど、普段からルーティンとして取り入れ、体に覚えさせることが重要です。そうすれば、緊張する本番でも意識的にリラックスできるようになります。
3. アファメーション(肯定的自己暗示)を唱える

アファメーションとは、自分にとって前向きな言葉を繰り返し唱えることです。
- 「私は自信を持って人前で話せる!」
- 「私は準備万端で、本番でも落ち着いていられる!」
- 「まあ、なんとかなるさ!」
たとえ今はそう思えなくても、意識してこれらの言葉を口に出したり、心の中で唱えたりしてみてください。自分が尊敬する人やプレゼンが上手い人の言葉を真似してみるのも良いでしょう。僕は一時期、そういった言葉を紙に書いて持ち歩き、ことあるごとに見ていました。
これも本番直前にやるだけでなく、普段から行うことが大切です。
例えば、先ほど紹介したスージングタッチをしながら「大丈夫、自分は準備万端だ」と唱えるなど、他のリラックス法と組み合わせるのも効果的。言葉が潜在意識に刷り込まれ、次第に自信が湧いてくるはずです。
人気漫画の主人公が「海賊王におれはなる!」と繰り返し言うように、言い続けることで、それが当たり前のように思えてくる効果があります。
4. 非言語コミュニケーションを強化する

プレゼンテーションは、話す内容(言語情報)だけが重要なのではありません。身振り手振り、目線、声のトーンといった非言語コミュニケーションも非常に大切です。
例えば、小さな声で縮こまって話していると、「自信がないのかな?」「この商品、本当に良いと思ってるのかな?」と相手に不安を与えてしまいますよね。逆に、堂々とした態度で、身振り手振りを交え、ハキハキと話すだけで、「この人は自信があるな!」「この人の話は説得力があるな!」と感じさせることができます。
僕も動画を撮影するときなどは特に、普段よりも少し声を張ったり、遠くにいる人に話しかけるように意識したりしています。また、体を動かすこと自体が緊張を紛らわす効果もあります。TEDのスピーカーがステージを歩きながら話すのも、そのためかもしれません。
普段の1対1の会話から、少しオーバーリアクション気味に身振り手振りを加えたり、声のトーンを意識したりする練習をしてみましょう。そうすれば、本番でも自然と非言語コミュニケーションを活かせるようになります。
5. 論理的思考(ロジカルシンキング)を強化する

論理的思考、つまりロジカルシンキングが苦手だと、話が分かりにくくなりがちです。「あれもこれも伝えたい!」と具体例をたくさん話した結果、「で、結局何が言いたいの?」と思われてしまうことがあります。
「あ〜、やっぱり何が言いたいのか伝えるのが苦手…」と思ってしまうと、プレゼンや人前で話すことに対しても苦手意識がどんどん強くなっていって、人前での緊張感も強まってしまいます。
論理的思考とは、物事を整理し、段階的に考えることです。
例えば、この記事も「人前で話すのが苦手」というテーマに対して、
- 人前で話すのが苦手 ↓
- 「考え方」
- 「習慣」
- 「事前対策」
- 「本番中のポイント」
というように、情報を分類して段階的に説明しています。さらに、「考え方」の中には
- 人前で話すのが苦手 ↓
- 「考え方」↓
- 「完璧主義を手放す」
- 「緊張して当然」
- 「習慣」
- 「事前対策」
- 「本番中のポイント」
- 「考え方」↓
といった具体的な項目がある、という構造になっています。
このような思考法を身につけるには、普段から「なぜそうなるのか?(Why?)」「どうすれば解決できるのか?(How?)」と自問自答する癖をつけるのがおすすめです。
例えば、「なぜ太ってしまうのか?」という問題に対して、「摂取カロリーが多いから」「消費カロリーが少ないから」と原因を分け、それぞれに対して「食事内容を見直す」「運動をする」といった対策を考える、というようにです。
いきなり具体的な話をするのではなく、
「まず、結論としてはこうです。その理由は〇〇で、具体的には△△のようなことがあります。だから、□□が大切なのです」
というように、話の骨組みを意識すると、聞き手にとって分かりやすい説明ができるようになります。
緊張を最小限に!プレゼン・人前で話すための4つの事前対策
どんなに考え方を変え、良い習慣を身につけても、やはり事前の準備は欠かせません。ここでは、本番での緊張を最小限に抑えるための具体的な事前対策を4つ紹介します。
1. カンペや資料をしっかり準備する

カンペや発表資料(パワーポイントなど)を準備しておくことは、安心材料として非常に有効です。何を話すかがある程度決まっていれば、それだけで心の余裕が生まれます。
ただし、ここでも完璧主義は手放しましょう。
カンペはキーワードだけをメモしておく程度にし、あとはアドリブに任せるくらいの気持ちでいると、かえって自然な話し方ができることもあります。資料があれば、「このスライドが来たらこの話をしよう」と、話の流れを思い出す助けにもなります。まっさらな状態で話すよりも、視覚的な手がかりがある方が圧倒的に話しやすいはずです。
そして最も重要なのは、
- 「この場で何を伝えたいのか」
- 「最終的な目的は何か」
を明確にしておくこと。これを忘れると、「みんなに緊張しているのがバレなければOK」というように、目的がすり替わってしまうことがあります。
2. 動画撮影で客観的に自分の話し方を確認する

これはめちゃくちゃ大事な練習法です。自分の話している姿を動画で撮影し、客観的に見てみましょう。
- 「意外と下を向きがちだな」
- 「こんな口癖があったのか」
- 「声が小さいな」
- 「もっと抑揚をつけた方がいいな」
など、様々な発見があるはずです。最初は恥ずかしいかもしれませんが、繰り返し行うことで、確実に話し方は上達します。プレゼン本番前の練習の時にも、一度動画で撮ってみることを強くおすすめします。自分の姿を見ることで、改善点が明確になり、効果的なインプットができます。
習慣として、毎日1分間スピーチや5分間スピーチを動画撮影するのも良いでしょう。これを続けるだけでも、話し方のスキルは飛躍的に向上するはずです。
3. 友人・家族・少人数、そして初対面の人と練習する

可能であれば、友人や家族など、気心の知れた相手の前で練習してみましょう。相手がいればフィードバックをもらえますし、本番に近い緊張感も体験できます。
「明日、ちょっと練習に付き合ってもらっていい?」とお願いして事前に予定を押さえてしまえば、強制力も働いて練習せざるを得ない状況を作れます。
そして、慣れた環境だけでなく、少し緊張するような初対面の人がいる場で練習することも非常に効果的です。
例えば、先ほどお話しした演劇のワークショップのような挑戦を必要とする会に参加したり、自分で少人数の勉強会を主催してみたりするのも良いでしょう。「苦手だな」と感じるタイプの人(例えば年上の男性など)がいる可能性のある場にあえて飛び込むことで、そういった相手にも慣れることができます。様々な人と話す経験を積むことが、自信に繋がります。
4. フレームワーク(型)を使って話の構成を考える

話の「型」であるフレームワークを使うと、分かりやすく説得力のある話がしやすくなります。ここでは代表的なものを2つ紹介します。
PREP(プレップ)法: PREP法は、結論を最初に伝え、その後に理由、具体例と続き、最後にもう一度結論で締めるという、非常にシンプルで分かりやすい構成のフレームワークです。特にビジネスシーンでの報告や提案、短いスピーチなどで効果を発揮し、相手に伝えたいことを簡潔かつ論理的に届けることができます。
P (Point – 結論): まず最初に、あなたが最も伝えたい主張や結論をズバリと述べます。聞き手は「これから何についての話なのか」を最初に把握できるため、その後の話がスムーズに頭に入ってきやすくなります。
- 例:「私は、あがり症を克服するためには、何よりも事前準備が大切だと考えています。」
R (Reason – 理由): 次に、なぜその結論に至ったのか、その根拠となる理由を具体的に説明します。この理由付けが、あなたの主張に説得力を持たせるための重要な土台となります。
- 例:「なぜなら、しっかりと準備を重ねることで、本番への自信が深まり、結果として過度な緊張を和らげることができるからです。」
E (Example – 具体例): そして、その理由を裏付けるための具体的な事例、データ、客観的な事実、あるいは個人的なエピソードなどを提示します。具体例を挙げることで、聞き手は話の内容をより鮮明にイメージでき、納得感も格段に高まります。
- 例:「例えば、以前カウンセリングを担当したAさんは、プレゼン前に何度もリハーサルを行い、想定される質問への回答も準備したところ、本番では落ち着いて堂々と発表でき、以前よりも格段に良い評価を得られました。」
P (Point – 結論): 最後に、もう一度、話の要点である結論を繰り返すことで、話全体を力強くまとめます。これにより、あなたが最も伝えたいメッセージが聞き手の記憶に残りやすくなります。最初の結論と全く同じ言葉でなくても構いませんし、行動を促すような一言を添えるのも効果的です。
- 例:「ですから、皆さんもプレゼンやスピーチの前には、ぜひ事前準備に時間をかけ、自信を持って本番に臨んでいただきたいと思います。」
DESC(デスク)法(提案型): DESC法は、もともとアサーティブコミュニケーション(自分も相手も大切にする自己表現)の場面でよく使われるフレームワークですが、プレゼンテーションや提案の場面でも非常に有効なんです。相手に何かを伝え、行動を促したいときに、スムーズで分かりやすい流れを作ることができます。
D (Describe – 描写する): まず、聞き手が直面している具体的な状況や、多くの人が共感できるような課題を客観的な視点から提示します。ここでの「描写」は、単に目に見えるものを写し取るだけでなく、聞き手が「まさにその通りだ」と感じるような状況や問題を明確に言語化することを含みます。例えば、「会議で緊張してうまく話せない」という多くの人が経験しうる具体的な状況を提示し、共感を引き出すことを意図しています。
- 例:「皆さん、会議で『もっと自分の意見を言いたいのに、緊張してうまく話せない…』と感じる、そんな経験はありませんか?」
E (Explain/Express – 説明する/表現する): 次に、その描写した状況がどんな影響をもたらすのかを説明したり、それに対する自分の考えや気持ちを表現することで、問題の重要性や放置することで起こりうるネガティブな側面を伝えます。
- 例:「その結果、良いアイデアがあっても伝えられず、チームに貢献できなかったり、後で『ああ言えばよかった』と後悔してしまうこともありますよね。」
S (Suggest/Specify – 提案する/具体的に示す): そして、その状況を改善するための具体的な解決策や行動を提案します。このとき、相手が取り組みやすい具体的な行動を促すことがポイントです。
- 例:「そこで提案なのですが、まずは今日の話の中から一つでも良いので、小さなことから実践してみませんか?例えば、深呼吸をする習慣をつけるとか、短いスピーチを録画してみるとか。」
C (Choose/Consequence – 選択してもらう/結果を伝える): 最後に、提案を受け入れた場合にどんな良い結果が期待できるかを伝えたり、相手に選択肢を示して選んでもらったりします。行動することで得られるメリットを明確にすることで、相手に「やってみようかな」と思ってもらうことがここでのゴールです。
- 例:「これらの方法を試すことで、少しずつ人前で話すことへの抵抗感が減り、自信を持って発言できるようになるはずです。もし、いきなり全部は難しいと感じるなら、まずは一番取り組みやすそうなものから選んでみてくださいね。」
このブログ記事の元になっているYouTube動画も、まさにこのDESC法に近い流れで構成されていますよね。「皆さん、こんな悩みはありませんか?(D)」と問題提起し、「そのままだと、こんな困ったことがありますよね(E)」と状況を説明し、「だから、こんな方法を試してみませんか?(S)」と様々な解決策を提案し、「この中から自分に合ったものを選んで、ぜひ実践してみてください。そうすれば、きっと良くなりますよ!(C)」と、行動を促し、その先にあるポジティブな変化を伝えています。
これらのフレームワークに当てはめて話の構成を考えると、自然と論理的で分かりやすいプレゼンができます。ぜひ活用してみてください。
いよいよ本番!緊張したときの3つの対処ポイント
どれだけ準備をしても、本番で緊張してしまうことはあります。そんなときに役立つ3つのポイントをお伝えします。
1. 聞き手の反応をしっかり見る(伝える相手を決める)

緊張すると、つい自分のことばかりに意識が向いてしまいます。「みんなに嫌われないかな」「どう思われているかな」と、自分の内側にこもってしまうのです。
そんなときは、意識して聞き手の反応を見てみましょう。特に、うんうんと頷いて聞いてくれている人や、優しい表情でこちらを見ている人を見つけて、その人に向けて話すようにすると良いです。伝える相手が明確になることで、「この人に届けよう」という気持ちが生まれ、自分の内側に向いていた意識が外側に向かいます。
「緊張して相手の顔なんて見れないよ!」と思うかもしれません。でも実は、相手の反応を見ていないからこそ、余計に不安になり緊張するという側面もあるんです。思い切って聞き手の顔を見てみましょう。意外とみんな真剣に聞いてくれていたり、あるいは全く別のことを考えていたり(笑)、あなたが思うほどあなたのことをジャッジしていないかもしれません。
2. 相手に話を振ってみる

ずっと一人で話し続けるのは、話し手も聞き手も疲れてしまいます。そんなときは、あえて聞き手に話を振ってみるのも一つのテクニックです。「〇〇さんはどう思いますか?」などと問いかけることで、場の注目がその人に移り、あなたは一時的にプレッシャーから解放されます。
また、聞き手を巻き込むことで、一方的なプレゼンテーションではなく、参加型の場を作ることができます。それによって、会場全体の緊張感が和らいだり、一体感が生まれたりすることもあります。
3. 声量・スピード・姿勢を意識的にコントロールする

緊張すると、声が小さくなったり、早口になったり、猫背になったりしがちです。これらは自信のなさを露呈し、さらに緊張を高めてしまう悪循環に繋がります。
本番中、もし「あ、緊張してきたな」と感じたら、意識的に以下の3点をコントロールしてみてください。
- 声量: 少し大きめの声で、ハッキリと話す。「皆さん、こんにちは!」と最初の挨拶を大きな声で言うだけでも、良いスタートダッシュが切れます。
- スピード: 緊張すると早口になりがちなので、意識してゆっくりと、間を取りながら話す。
- 姿勢: 背筋を伸ばし、胸を張る。堂々とした姿勢は、自信があるように見せるだけでなく、実際に自分自身のメンタルにも良い影響を与えます。
「緊張してきたな」と思ったら、逆に自信があるように振る舞ってみる。クリスティアーノ・ロナウド選手がPKを蹴る前のような堂々とした態度をイメージするのも良いかもしれませんね(伝わるかな?笑)。
おわりに:今日からできる一歩を踏み出そう!
さて、ここまで人前で緊張しないための考え方、習慣、事前対策、そして本番中のポイントについてお話ししてきました。たくさんの情報をお伝えしましたが、大切なのは、この中から一つでも良いので「実践してみる」ことです。頭で理解するだけでなく、実際に行動に移して初めて変化が生まれます。
「完璧じゃなくていいんだ」
「緊張するのは当たり前なんだ」
「聞き手は意外と優しいのかもしれない」
そんなふうに少しでも考え方が変わったり、「深呼吸を試してみようかな」「明日、自分のスピーチを動画で撮ってみようかな」と、具体的な行動を起こすきっかけになったりしたら、僕もとても嬉しいです。
あがり症や人前で話すことへの苦手意識は、決してあなた一人の問題ではありません。多くの人が同じような悩みを抱えています。そして、正しい知識とトレーニングを積めば、克服していくことができます。焦らず、自分のペースで、今日からできる小さな一歩を踏み出してみてくださいね。応援しています!
この記事を読んで、「もっと具体的に知りたい!」「自分一人ではなかなか変われないかも…」と感じた方もいるかもしれません。
そんなあなたのために、僕、ザッキーが「対人恐怖症・脇見恐怖症改善のための3日間無料動画講座」をプレゼントしています!
この動画講座では、
- あがり症や対人恐怖症を改善するために本当に必要な要素
- 具体的な改善プロセス
- 改善のための具体的な方法を日常にどう落とし込むか
といった内容を、分かりやすくお伝えしています。特に、僕自身が過去に脇見恐怖症で悩んでいた頃の経験からの学びや、これまで多くのクライアントさんと接してきた中での具体的な事例なども交えながらお話ししているので、きっとあなたにも「自分ごと」として受け取っていただけるはずです。
この動画講座は、過去の僕と同じように悩んでいる方たちの力になりたいという強い思いで作成しました。正直なところ、将来的には配信をストップするか、有料に切り替える可能性も高いです。ですので、この機会を逃さず、ぜひ無料でお受け取りいただければと思います。
「本気で自分を変えたい」「もう緊張や不安に振り回される人生は嫌だ」
そう思っているあなたの、最初の一歩をサポートできれば幸いです。
ご興味のある方は、ぜひ下記のバナーから僕の公式LINEに登録して、動画講座をご覧ください!